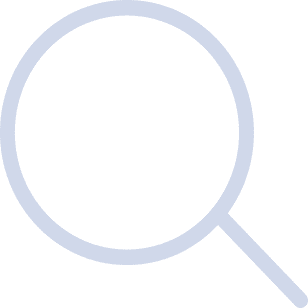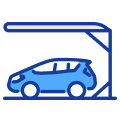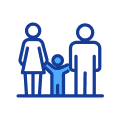賃貸アパートでもできる防音対策とは?自分でできる方法や防音アイテムをご紹介

静かに暮らしたい――そう思っても、アパートでは「隣や上階の音」「自分の生活音」が気になることがあります。「足音や話し声が響かないかな」「防音性は大丈夫だろうか」――アパート生活に、そんな不安を抱く人は少なくありません。
実は、防音性能は建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)によって大きく異なります。 この記事では、アパートの防音性の仕組みと、賃貸でも実践できる防音対策・マナーを具体的に紹介。静かで心地よい住まいをつくるためのヒントをお届けします。
目次
賃貸アパートにおける防音対策で知っておくべきポイント
賃貸アパートとは、一般的に木造や軽量鉄骨造で建てられた2階建て前後の集合住宅を指します。 マンション(鉄筋コンクリート造)に比べると構造材が軽く、音や振動を伝えやすいのが特徴です。
とはいえ、「構造上の特徴を理解し、音の伝わり方を知る」ことで、自分でも十分に対策できます。 もし、お部屋さがしの中で気に入った物件がアパートであっても、防音の仕組みを知り、対策を取り入れることで、快適に暮らすことは十分可能です。
まずは、日常生活で起こりやすい騒音の種類とその仕組みを整理してみましょう。
2種類の騒音について理解する
アパートで発生する音には、大きく分けて2つの伝わり方があります。
| 音の種類 | 特徴 | 代表的な例 | |
|---|---|---|---|
| 固体伝搬音 | 音の種類:固体伝搬音 | 特徴:建物の構造を通じて伝わる音 | 代表的な例:足音・ドアの開閉・洗濯機の振動 |
| 空気伝搬音 | 音の種類:空気伝搬音 | 特徴:空気中を振動して伝わる音 | 代表的な例:話し声・テレビ・ペットの鳴き声 |
固体伝搬音
「固体伝播音」とは、床や壁、柱などの構造体を通じて伝わる音のこと。上階の足音やイスを引く音が、「ドン」「ゴトッ」と低音で響きます。構造体そのものが振動するため、響きやすく消えにくいのが特徴です。木造や軽量鉄骨造では素材が軽いため、振動が伝わりやすい傾向があります。
- 防音マットやカーペットで衝撃を吸収
- 洗濯機や家具の下に防振ゴムを敷く
- 厚手ラグや吸音ボードで振動を緩和する
対策のポイント
空気伝搬音
「空気伝播音」とは、空気中を振動して伝わる音のこと。人の声やテレビの音が壁や窓を通じて伝わります。木造・軽量鉄骨造では壁の厚みが薄く、断熱材が少ないため、音漏れしやすい構造です。
- 厚手カーテンや吸音パネルで音を吸収する
- 本棚・家具を壁際に置き反射を防ぐ
- 隙間テープで窓やドアの開口部をふさぐ
対策のポイント
「固体伝搬音」「空気伝搬音」いずれの対策も、自分の生活音を抑えると同時に、隣室からの音も和らげられる工夫になります。
木造の場合は音を伝えやすく遮音性が低い
木造アパートは、柱や梁などの主要構造に木を使用した建物です。木は温かみのある素材ですが、振動を伝えやすく、吸音しにくい性質を持っています。そのため、上階の足音や壁越しの声が響きやすい傾向があります。
また、木造は鉄筋コンクリート造に比べて壁や床が薄く、密閉性も低いため、音が伝わりやすい構造です。 特に築年数の経った建物では、隙間の増加や素材の劣化によって遮音性がさらに低下する場合もあります。
ただし、最近では石膏ボードの多層化や断熱材の充填により性能が向上しています。さらに、防音マットや防音カーテンなどを組み合わせることで、「防げない音」ではなく「抑えられる音」へと変えていくことができるでしょう。
賃貸アパートでもできる防音対策
アパートの構造上、完全に音を遮断することは難しくても、日常の工夫で音の伝わり方を軽減することは可能です。 近隣からの生活音に悩まされている人も、自分の出す音が気になる人も、ちょっとした対策で快適さは大きく変わります。
ここでは、賃貸でも簡単に取り入れられる防音アイテムや実践方法を紹介します。 大掛かりなリフォームをしなくても、今日から始められる工夫で"音ストレス"を減らしましょう。
防音マットを敷く
床から伝わる足音や振動を抑えるには、防音マットの設置が効果的です。 床と家具の間にクッションの役割を持たせることで、固体伝搬音の発生を軽減できます。
リビングや寝室など、歩く頻度の高い場所に敷くだけでも効果があり、カーペットやラグの下に重ねるとさらに吸音性が高まります。厚みや素材によって効果が異なるため、遮音等級や材質(ゴム・コルクなど)を確認して選ぶのがポイントです。
なお、ゴム製マットの中には可塑剤によってクッションフロアを変色させるものもあるため、ノンブリード仕様やフェルト素材など、床材にやさしいタイプを選ぶようにしましょう。
吸音材を貼り付ける
壁や天井に反射して響く空気伝搬音を抑えるには、吸音材を貼る方法が効果的です。声やテレビの音が外に漏れにくくなり、室内の反響も軽減できます。
賃貸の場合は、貼ってはがせる弱粘着タイプや、マスキングテープを併用して固定できるものを選ぶと安心です。
ウレタンやフェルト素材などデザイン性の高い製品も多く、防音とインテリア性を両立できます。テレビ背面や話し声が響きやすい壁など、部分的に取り入れるのもおすすめです。
隙間テープを活用する
ドアや窓のわずかなすき間は、音が出入りする大きな経路になります。そこで役立つのが、貼るだけで簡単に防音できる「隙間テープ」です。すき間をふさぐことで、外からの話し声や車の音を軽減し、自分の生活音も漏れにくくなります。
防音だけでなく、冷暖房効率の向上や防塵効果も期待できるのが魅力です。貼る場所に合わせてゴム・スポンジなど素材を選び、開閉のしやすさを保ちながら施工するのがポイントです。
洗濯機の下に防振ゴムを設置する
洗濯機の脱水時に発生する振動やモーター音は、床を通じて建物全体に響きやすいものです。特に木造や軽量鉄骨造では、この振動が下階に伝わり、「ゴトゴト」という固体伝搬音の原因になります。
そこで有効なのが、防振ゴムの設置です。洗濯機の脚の下に敷くことで、床との接触をやわらげ、振動を吸収できます。高さのあるタイプなら通気性も確保でき、カビ防止や床の傷防止にも効果的。
手軽に取り入れられる防音対策としておすすめです。
防音カーテンを活用する
窓は、外からの音が入りやすく、室内の音が漏れやすい場所のひとつです。
そこで効果的なのが、防音カーテン。厚手の多層構造生地が音の振動を吸収し、車の走行音や話し声の侵入を軽減します。同時に、室内の声やテレビの音も外に漏れにくくなるため、プライバシー対策にも有効です。
取り付ける際は、窓枠全体を覆う長さと幅のカーテンを選ぶのがポイント。遮光性や断熱性を兼ね備えたタイプなら、快適性と節電効果も期待できます。
賃貸アパートで騒音トラブルを避けるポイント

どれだけ気をつけていても、生活音を完全に消すことは難しいもの。
しかし、ちょっとした心がけや時間帯への配慮で、騒音トラブルは防ぐことができます。特にアパートのように住戸同士が近い環境では、相手の立場を想像する気持ちが大切です。
ここでは、日常生活の中で実践できる音へのマナーと工夫のポイントを紹介します。自分も周りも気持ちよく暮らせる環境づくりを意識してみましょう。
夜間の洗濯機の使用を避ける
夜間に洗濯機を回すと、周囲が静かなぶん音が響きやすく、振動やモーター音が床や壁を伝って広がりやすくなります。特に木造や軽量鉄骨造のアパートでは、脱水時の揺れが固体伝搬音として下階や隣室に届くこともあります。
夜は日中に比べて環境音が少ないため、小さな音でも気になりやすいもの。できるだけ昼間や夕方に使用し、やむを得ず夜間になる場合は、防振ゴムを敷く、タイマーで早朝に回すなどの工夫で配慮しましょう。
窓を開けた状態で大きな音を出さない
窓を開けたままの状態では、声やテレビの音、咳払いなどの日常的な音も空気中を伝って外に漏れやすくなります。特に高い声や大きな話し声は想像以上に響き、周囲の生活空間まで届くことも。また、夜間や早朝は街が静かなぶん、音の距離感が広がりやすいため注意が必要です。
換気や通風が必要なときは、短時間で済ませる、音量を抑える、防音カーテンを併用するなど、周囲への配慮を心がけましょう。
まとめ
アパートでの暮らしは、建物の構造や環境によって音の感じ方が変わります。たしかに、木造や軽量鉄骨造はコンクリート造に比べて防音性で劣る面もありますが、工夫次第で快適な住まいは十分に実現可能です。
防音マットやカーテンなどのアイテムを活用し、時間帯や音量への配慮を心がけるだけでも、生活音のストレスは大きく減るでしょう。また、自分の音を抑える工夫は、隣人からの音も感じにくくする効果があります。
防音性だけで物件を諦めず、立地や設備とのバランスを考えながら、対策を取り入れてみてください。ちょっとした工夫が、アパートでも「音を気にせず心地よく暮らせる空間」をつくります。
お部屋探しの際は、内見時に壁や床の厚み、窓の構造などもチェックしてみましょう。