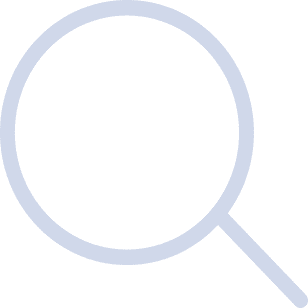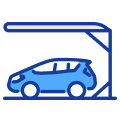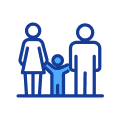鉄筋コンクリート造(RC造)の防音性能はどれくらい?防音対策と合わせてご紹介

「上下や隣の部屋の音が気になる」「静かに暮らせる物件ってないの?」
そんなお悩みから、防音性の高い住まいを探している方も多いのではないでしょうか。賃貸物件を探す際には、生活音によるストレスやトラブルを避けるため、建物の構造に注目することが大切です。
中でも「鉄筋コンクリート造(RC造)」は、防音性に優れているといわれる構造のひとつですが、実際のところはどうなのでしょうか?
この記事では、鉄筋コンクリート造の防音性能の特徴や、防音対策のポイントについてわかりやすく解説します。音の悩みから解放され、快適な暮らしを実現するためのヒントとして、ぜひご覧ください。
目次
鉄筋コンクリート造(RC造)の防音性能とは
住まい選びで「静かに暮らせるかどうか」は非常に重要なポイントです。
特に集合住宅では、隣人や上下階の生活音がストレスになることも少なくありません。そこで注目されるのが「鉄筋コンクリート造(RC造)」の物件です。鉄筋コンクリート造は、防音性に優れているとされる建物構造の代表格ですが、その理由はどこにあるのでしょうか?
鉄筋コンクリート造の基本構造
鉄筋コンクリート造とは、鉄筋とコンクリートを組み合わせて作られた建物構造のことです。
コンクリートという素材は密度が高く、音を通しにくい性質を持っています。
さらに骨組みとなる鉄筋の回りに型枠を立て、コンクリートを流し込み固める鉄筋コンクリート造では、壁や床が厚く造られているため音が伝わりにくく、隣室や上下階からの生活音が軽減されやすいのが特徴です。
また、建物を支える骨組み部分そのものがしっかりしているため、振動音や衝撃音も抑えられる傾向があります。
木造・鉄骨造との防音性能の違い
木造や軽量鉄骨造と比べると、鉄筋コンクリート造の防音性は格段に高いといえます。
木造住宅は構造材が軽く、壁も薄い傾向があるため、話し声や足音、生活音が響きやすくなります。また鉄骨造も振動音が伝わりやすい傾向があります。
一方、鉄筋コンクリート造は壁厚があり、音を吸収・遮断する力が強いため、音のトラブルを避けたい方にとっては安心につながる選択肢といえるでしょう。
鉄筋コンクリート造(RC造)でも音が気になるケース
防音性の高さが魅力の鉄筋コンクリート造(RC造)ですが、「鉄筋コンクリート造に住んでいるのに、意外と音が気になる」と感じるケースも実際にはあります。
確かに鉄筋コンクリート造は基本構造としては防音、遮音性に優れているものの、すべての物件が完全に静かな環境を保証するわけではありません。
その差には、建物の築年数や施工方法、壁の構造などが大きく関係しているのです。
築年数が古い建物は防音性能が低い
鉄筋コンクリート造でも、築年数が古い物件では防音性能が十分でないことがあります。
特に築30年以上の建物では、コンクリートの厚みが十分でなかったり、施工方法も遮音性が著しく低いものであったりと、現在の基準に比べて防音性が劣るケースが多く見られます。
一方で、2000年築以降の建物なら隣接する住戸を区切る壁に高い遮音性能を持つものが使用されています。防音性を重視するなら、2000年築以降の鉄筋コンクリート造を選ぶことがポイントです。
壁の工法による防音性能の差
もう一つ、防音性に大きく影響するのが「壁の工法」です。鉄筋コンクリート造には「ラーメン構造」と「壁式構造」という代表的な工法があり、特に防音性の違いが現れやすいのはこの部分です。
「ラーメン構造」では柱と梁で建物を支えるため、間取りの自由度が高い反面、間仕切り壁が比較的薄く、防音性がやや劣る傾向があります。一方、「壁式構造」は厚い壁で建物を支える構造で、遮音性に優れているため、音が伝わりにくいのが特徴です。
さらに、壁の材質や厚み、サッシや窓ガラスの種類によっても音の伝わりやすさは変わってきます。たとえ鉄筋コンクリート造でも、隣室との間にある壁が「GL工法」と呼ばれるコンクリート壁にGLボンドと呼ばれる接着剤で石膏ボードを貼り付ける工法であったり、窓があまりにも薄いガラスであったりすると、音漏れの原因となる可能性があります。
こうした点は、物件選びの際に見落とされやすいため、防音性を重視する場合は工法や仕様も事前に確認することが大切です。
防音性の高い鉄筋コンクリート造(RC造)物件の見つけ方

鉄筋コンクリート造(RC造)は、防音性の高さが魅力とされる構造ですが、すべての鉄筋コンクリート造物件が「静かに暮らせる」とは限りません。
実際に住んでみてから「思ったより音が響く......」と感じることもあるため、物件選びの段階で防音性をしっかりと見極めておくことが大切です。
ここでは、内見時にできる簡単なチェック方法や、事前に確認しておきたいポイントを紹介します。
壁を叩く
内見時には、壁を軽くノックしてみましょう。
「コンコン」と低くつまった音で響かなければ防音性の高い直張りのコンクリート壁。一方、数箇所叩いてみて「コツコツ」「ゴツゴツ」とランダムに異なる音がする場合は、古い物件でよく見られるGL工法(コンクリート壁+石膏ボード)が疑われます。GL工法は遮音性能が大きく低下する傾向があることが確認されています。
違いがわからない場合は、不動産会社に壁の工法や防音仕様を尋ねてみても良いでしょう。
部屋の中で手を叩く
窓を閉めた室内の中央で手を叩いて、音の響き方を確認するのも一つの方法です。
音がよく反響するような感覚がある場合は、安心です。壁・床・天井が強固に構成されていて、一般的に防音性が高い住戸といえます。そうでない場合は、壁や隙間を通して音が外に漏れている可能性があります。
これは簡易的なチェックですが、住んだ後の体感にも影響するポイントです。
騒音トラブルの有無について確認する
内見時には、不動産会社の担当者に「過去にこの物件で騒音トラブルはありましたか?」と聞いてみるのも有効な場合があります。
もし過去に隣人トラブルや苦情が頻繁に発生していた場合、物件そのものの防音性に問題がある可能性もあるからです。もしかすると「上の階の足音が気になる」「生活音が筒抜けだった」といったことが原因という場合もあるかもしれません。
入居者の属性が子育て世帯メインなのか、単身者が多いかによっても、音の感じ方や許容度に違いが出るため、事前情報は貴重な判断材料の一つになります。
鉄筋コンクリート賃貸で快適に暮らすための防音対策
鉄筋コンクリート造(RC造)の賃貸物件は、一般的に防音性が高いと言われていますが、まったく音が気にならないわけではありません。
しかし構造上の防音性能に加え、住む人自身ができる対策を取り入れることで、より快適な住環境が整います。ここでは、鉄筋コンクリート賃貸で快適に暮らすための具体的かつハードルの低い方法を紹介します。
吸音材を活用する
室内で音が響きやすいと感じた場合、まずは「吸音材」の導入を検討してみましょう。
壁に貼るタイプの吸音パネルや、床に敷く防振マット、厚手のラグ・カーペットなどは、音の跳ね返りを抑える効果があります。
最近ではデザイン性の高い商品も増えており、インテリアのポイントも兼ねた対策ができるのも魅力です。
観葉植物を設置する
意外に思われるかもしれませんが、観葉植物も防音対策として有効です。
葉や土、鉢などが音を吸収したり分散したりすることで、室内の反響音をやわらげる効果があります。
特に、背の高い植物を窓辺や部屋の隅に配置することで外からの騒音の進入を緩和する役割も果たします。緑のある空間はリラックス効果も高まるため、防音だけでなく快適な住環境づくりにも一石二鳥です。
防音カーテンを設置する
窓からの外部音が気になる場合には、防音カーテンの導入がおすすめです。
厚手で密度の高い生地で作られた防音カーテンは、音の出入りを軽減してくれる効果があります。特に、交通量の多い通り沿いや線路の近くに住んでいる場合は、その違いを実感しやすいでしょう。
また、防音カーテンには遮光性・断熱性を兼ね備えたタイプも多く、冷暖房効率のアップにもつながります。機能性と快適性を兼ね備えたアイテムとして、導入のハードルも低めです。
まとめ
鉄筋コンクリート造の建物は、防音性に優れているものの、音の悩みがゼロとは限りません。
快適な住まいを実現するためには、吸音材の活用や観葉植物の設置、防音カーテンなど、身近な対策を取り入れることも効果的です。音のストレスを減らすことで、日々の生活の満足度もぐんと高まります。物件の構造だけでなく、自分自身でできる工夫も取り入れながら、静かで心地よい住環境を整えていきましょう。