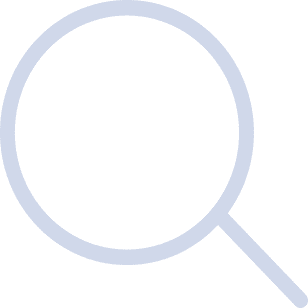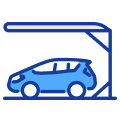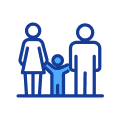賃貸物件の「ハイツ」とはどんな物件?マンションとの違いやメリットについてご紹介

ネットなどで賃貸物件を探していると、「○○ハイツ」という名前を目にすることがあります。ただ、「ハイツ」とは具体的にどんな建物なのか、よく分からない......という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「ハイツ」と呼ばれる賃貸物件の一般的な特徴から、マンションとの違い、そしてハイツに住むメリット・デメリットまでを分かりやすくご紹介します。
自分に合った住まい選びの参考に、ぜひチェックしてみてください。
目次
「ハイツ」とは
「ハイツ」とは、賃貸物件の建物名称に使われることが多い呼び名の一つですが、マンションやアパートのように法律などで明確に定義されている言葉ではありません。
一般的には、軽量鉄骨や木造で建てられた2階建て程度の低層集合住宅を指すことが多く、名前から受ける印象として「小規模で落ち着いた住まい」をイメージされやすい特徴があります。
そもそも「ハイツ」という言葉自体は、英語で「高台」を意味する"heights"が由来といわれています。日本では、「高級感」や「おしゃれな雰囲気」を演出するために、1980年代以降に建てられた賃貸住宅で広く使われるようになりました。
そのため、実際の立地や構造が「高台」にあるとは限らず、単に物件名の一部として付けられているケースがほとんどです。地域によってはアパートの代わりに「ハイツ」という名称が主流になっているところもあります。つまり「ハイツ」とは、特定の規格を表す言葉ではなく、建物名やコンセプトを表現するための一種の"ネーミング"にすぎません。
賃貸探しの際には、名称にとらわれず、構造や設備、家賃などをしっかり確認することが大切です。
ハイツ物件のメリット
上記の通り「ハイツ」という名前のついた物件には、明確な建築基準があるわけではないものの、一般的に、軽量鉄骨造や木造の2階建て程度の集合住宅を指すことが多いとされています。
いわば、おしゃれな雰囲気を演出するための呼称として物件に付けられてきた「ハイツ」ですが、そうした物件に感じられることの多い「良さ」がいくつかあります。
ここでは、ハイツ物件ならではの利点を整理してご紹介します。
家賃が比較的安い
ハイツ物件の大きなメリットのひとつが、家賃の安さです。
鉄筋コンクリート造のマンションに比べて建築コストが低い木造や軽量鉄骨で建てられることが多いため、同じ広さや間取りでも家賃が抑えられる傾向にあります。できるだけ住居費を抑えたい人にとっては、経済的に大きな魅力となります。
浮いた分の予算を家具や家電、日々の生活費に回すことができるのも利点です。
小規模で落ち着いた環境が多い
ハイツ物件は小規模な集合住宅であることが多く、住民数も限られています。
そのため、大規模マンションに比べて人の出入りが少なく、こじんまりと落ち着いた住環境が得られやすい点もメリットです。同一物件に暮らす住民が比較的少ないため、「住人同士で顔を覚えられるくらいの距離感に安心感がある」と感じる人もいます。
また2階建て物件の場合、上下左右どこかに必ず他の住戸と接していない面があるため、隣人等へのストレスを感じにくいという面もあります。
日当たりや風通しがいい
ハイツ物件は低層住宅が多く、周囲に高い建物が少ない立地に建てられている場合も少なくないため、日当たりや風通しの良さが期待できる点も魅力です。
特に2階部分は、マンションの低層階よりも光が入りやすく、明るく開放的な住空間を実現できます。風通しが良ければ室内に湿気がこもりにくく、カビや結露の発生を防ぐ効果も期待できます。
自然光を取り入れながら快適に暮らしたい人や洗濯物を外に干すことが多い人にとっては、特にメリットが大きいでしょう。
ハイツ物件のデメリット

ハイツ物件には、家賃の安さや日当たりの良さといった魅力があります。しかし一方で、建物の構造や築年数に由来するデメリットも存在します。
住み始めてから「思ったよりも生活しにくい」と感じるケースもあるため、メリットだけでなく注意点も知っておくことが大切です。
ここでは、ハイツ物件でよく指摘されるデメリットを3つに分けて解説します。
遮音性が低い
ハイツ物件の多くは木造や軽量鉄骨造で建てられているため、鉄筋コンクリートなどで造られるマンションに比べて遮音性に劣る傾向があります。
上階の足音や隣室の生活音、テレビの音などが響きやすく、自分の生活音が周囲に漏れてしまう可能性もあります。特に夜間は小さな物音でも気になってしまい、静かな環境を求める人にとってはストレスになるかもしれません。
生活時間帯が異なる住民が多い建物ではトラブルの原因となることもあるため、入居前に周囲の音環境を確認しておくと安心です。
断熱性や気密性に劣る
木造や軽量鉄骨造は構造的に断熱性・気密性が低い傾向にあり、室内の温度が外気の影響を受けやすいのもデメリットのひとつです。
夏は室内が暑くなりやすく、冬は冷え込みが厳しくなるため、冷暖房費が増えてしまうことがあります。また、気密性が低いと隙間風を感じやすかったり、湿気や結露が発生しやすい環境になる場合もあります。
快適な室内環境を保つためには、断熱性の高いカーテンを利用したり除湿機を置くなどの工夫が必要な場合もあります。
築年数の古い物件が多い
「ハイツ」という名称は1980年代以降に広く使われるようになり、現在では築30年以上の物件も少なくありません。
そのため、ハイツ物件には築年数が古い物件が多いという現状があります。間取りが現在の生活スタイルに合わなかったり、収納スペースが限られていたりすることもあり、利便性を求める人には不便に感じられるかもしれません。
さらに古い木造物件では耐震性への不安もあります。築年数が古い分家賃が安いという利点はありますが、長期的な住み心地を重視するなら注意が必要です。
ハイツが向いている人の特徴
建物の構造やタイプによって、賃貸物件の住み心地は大きく変わります。
その中で「ハイツ」と呼ばれる物件は、木造や軽量鉄骨造の低層住宅が多く、鉄筋コンクリート造等のマンションとは異なる特徴を持っています。
では、どのような人がハイツ物件に向いているのでしょうか。ここでは代表的な特徴を2つに分けてご紹介します。
低層階に住みたい人
ハイツ物件の多くは2階建ての低層住宅です。高層階が存在せず、地面に近い生活ができる点が特徴といえるでしょう。
落下事故が心配な小さなお子様がいる家庭や、上下移動が負担になる高齢の方にとっては安心感があります。また、「ゴミ出しが楽」「地震などの災害時に避難しやすい」というメリットもあります。
ハイツ物件はエレベーターのない物件がほとんどですが、逆に「低層階の落ち着いた暮らしをしたい」と考える人には適した環境といえるでしょう。
家賃をなるべく抑えたい人
ハイツ物件はマンションに比べて建築コストが低く抑えられることから、同じエリアや広さでも比較的家賃が安い傾向にあります。
そのため、初めての一人暮らしや、出費をできるだけ抑えたい方に向いています。さらに、築年数が経過している物件を選べば、相場よりも安い家賃で広めの間取りを借りられる可能性もあります。
「できるだけ居住コストを抑えて、そのほかのことに予算を回したい」という人には、ハイツは現実的な選択肢となるでしょう。
まとめ
「ハイツ」とは、一般的に木造や軽量鉄骨造で建てられた低層住宅を指すことが多いものの、実は法律や建築基準で明確に定められた用語ではありません。
マンションやアパートのように構造や規模で区別されるものではなく、あくまで物件名に使われる"呼び名"のひとつに過ぎません。そのため、「ハイツ」と名前が付いていても、建物の構造や設備は物件によって大きく異なる場合があります。家賃が比較的安く、小規模で落ち着いた環境が多い傾向はありますが、それが必ずしもすべての「ハイツ」に当てはまるわけではありません。
物件探しの際は名前だけで判断せず、築年数や遮音性、日当たり、周辺環境など、実際の条件を確認することが大切です。